出資をする際、出資金が集まらないあまり銀行とグルになったり第三者を使ってうまくごまかす人が出てきます。
そのごまかしのことを払込の仮装といいます。
払込の仮装は2種類あります。
※預合(あずけあい)
預金(100万)
A株式会社![]() B銀行
B銀行
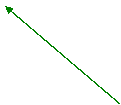
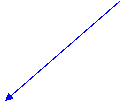
発起人C
(100万)
まず発起人CとB銀行がグル(通謀といいます。)になり、帳簿上の振替を行います。
つまり、CがBから出資金に足りないお金(ここでは仮に100万)を借ります。(借入)
そして、Aに払込をするためにBに100万を預けます。
実際に現金を動かすのは面倒で意味がないので、Bは帳簿の上でCからの払込を受けます。
ここで問題なのは、実際にA株式会社が出来て、出資された100万を使おうとしても使えないわけです。
自分の会社のお金なのに使えないというおかしなことが起きます。
なぜなら、BはCに貸した100万を担保としているのでCがBに100万返さない限り使えないからです。
これは商法上の犯罪になります。
| 第965条 第960条第1項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。 |